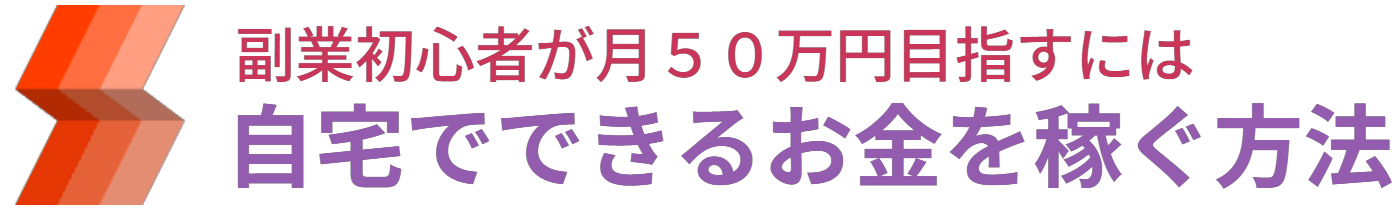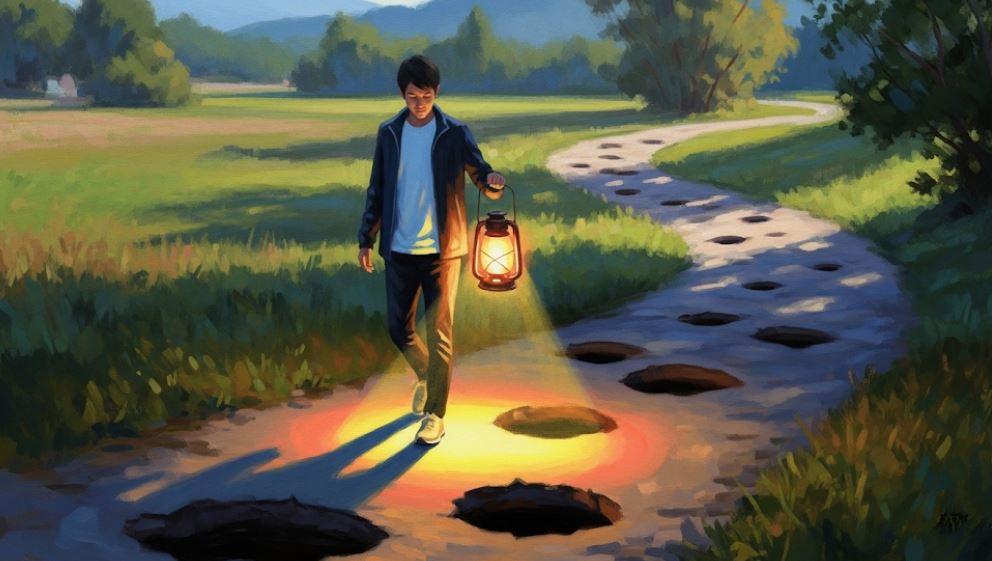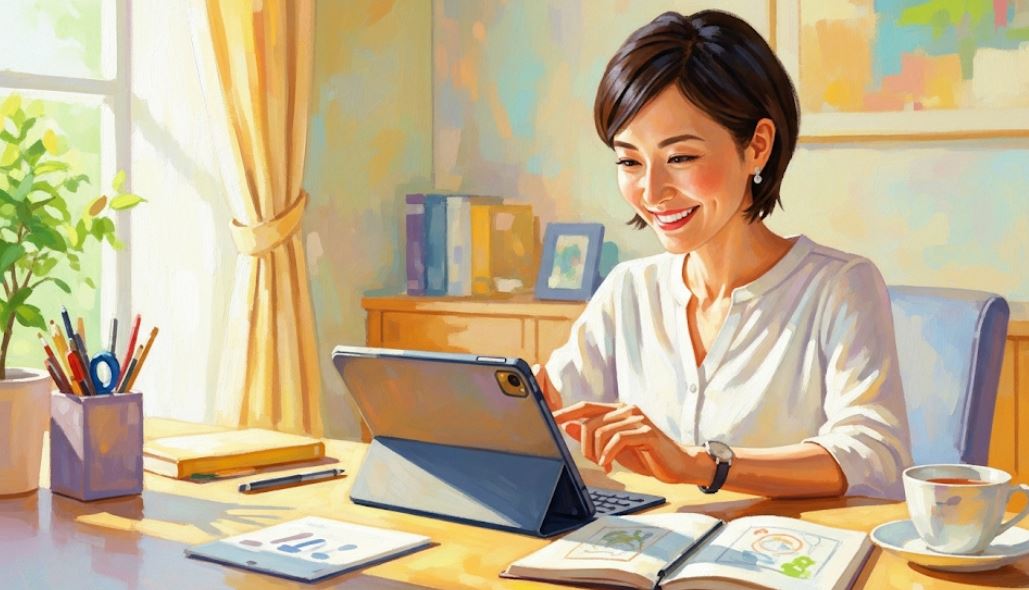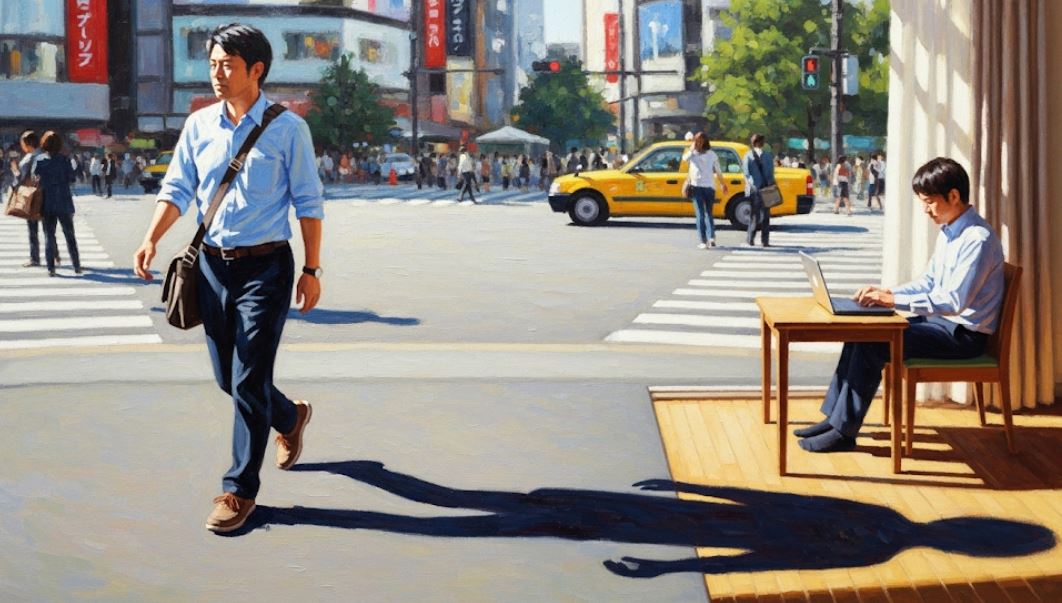なぜ介護士は給料が低いのか?5つの理由と収入を上げる方法

いやどうも!
タケパトです!
いきなりですけどね、アナタ、今、お金のことで悩んでますよね?
特に、「なぜ介護士は給料が低いんだ!」って、やり場のない怒りとか、将来への漠然とした不安を抱えながら、このページにたどり着いたんじゃないかと思うんですよ。
分かります、分かりますよぉ。
その気持ち、痛いほど分かります。
ボクも昔は、アナタと全く同じでしたから。
ただの中小企業のサラリーマンで、毎月給料明細を見てはため息をついて、妻と共働きでなんとかカツカツの生活を送っていました。
でもね、ある日、ボクの人生を根底から揺るす、とんでもない事件が起きたんです。
それは数年前のこと。
当時まだ小さかった最愛の息子が、突然高熱を出して、ぐったりして動かなくなったんです。
慌てて病院に駆け込んだら、お医者さんから告げられた病名は「敗血症」。
…一瞬、頭が真っ白になりましたね。
命に関わる、ものすごく危険な状態だって言うじゃないですか。
集中治療室に運ばれて、小さな体にたくさんの管をつながれた息子を見て、ボクはもう、何も考えられませんでした。
仕事なんて、どうでもよくなりました。
ただただ、息子のそばにいたい、妻を支えたい。
でもね、現実は非情ですよ。
会社は休ませてはくれるけど、その間の給料は出ない。
どんどん減っていく有給休暇の日数と、増え続ける治療費の請求書を前に、ボクは心底、自分の無力さを呪いましたね。
「家族一人の命も、お金の心配なく守れないのか…」って。
この経験が、ボクの目を覚まさせたんです。
会社に依存して、決められた給料をもらうだけの人生は、あまりにもろくて危険なんだと。
自分の、そして家族の人生のハンドルは、自分で握らなきゃダメなんだって。
そこからボクは、わらにもすがる思いで、時間と場所を選ばずに稼げる方法を探し始めました。
そしてたどり着いたのが、スマホ一台で始められるアフィリエイトだったんです。
今では、会社を辞めて、家事や子育ての合間にスマホをポチポチするだけで、月100万円以上を安定して稼げるようになりました。
だからね、ボクは自信を持って言えるんです。
アナタが今抱えている「なぜ介護士は給料が低い」っていう悩みは、解決できる!
この記事では、まずアナタが直面している介護業界の給料が低い構造的な問題を、ボクなりに分かりやすく解説します。
そして、その上で、そんな八方ふさがりの状況から抜け出して、経済的な自由と心の平穏を手に入れるための、超具体的な方法を、ボクの全経験を込めてお伝えします!
ちょっと長くなるかもしれないけど、まあ、騙されたと思って、最後までついてきてくださいよ!
アナタの人生、ここから変わるかもしれませんから!
この記事を読んで分かること
- なぜ介護士は給料が低いのか、その根本的な理由
- 国の制度が給料にどう影響しているかの仕組み
- 介護の仕事の専門性が給与に反映されない問題点
- 人手不足なのに給料が上がらないという矛盾のカラクリ
- 給料を上げるための具体的なキャリアアップ方法
- 会社や制度に頼らず個人で収入を爆上げする秘策
- 絶望的な状況からでも人生を逆転させるチャンスがあること
========================
【PR】 タケパトのおすすめアフィリエイト教材
Tipsビジネスランキング1位!
資金なし、スキルなし、知識なしでもできる!初心者向け
X(ツイッター)とスマホだけで簡単副業!
爆速収益化!3ヶ月で月30万円 1年で月100万円目指せる
詳しい教材のレビューはこちら
なまいきくん流X運用術【The.X】)))))))))))))).jpg)
================
なぜ介護士は給料が低いのか?その構造的な問題を解説
この章のポイント
- 給料の源泉「介護報酬」という国の仕組み
- 専門性が正当に評価されにくい現状
- 人手不足なのに給料が上がらないパラドックス
- 非正規職員の多さが平均給与を下げる一因
- 仕事内容と給与のバランスが取れていない
給料の源泉「介護報酬」という国の仕組み

さあさあ、まず最初のテーマですよ!
アナタが「なんでこんなに頑張ってるのに給料が安いの!」って叫びたくなる、その根本原因にズバッと切り込んでいきましょう。
ボクもね、サラリーマン時代は自分の給料がどうやって決まるのかなんて、正直あんまり深く考えてませんでした。
でも、この問題は知っておかないと、ただ文句を言うだけで終わっちゃいますからね。
まず、一番大事なキーワード、それが「介護報酬」です。
なんだか難しそうな言葉ですけど、要は、アナタの働いている介護施設や事業所が、国(というか市町村)から受け取るサービス代金のことなんですね。
普通の会社だったら、例えばラーメン屋さんなら、ラーメン一杯800円とか、自分たちで値段を決められるじゃないですか。
もっと儲けたいなら、味を良くして1000円に値上げする!
なんてことも可能です。
でも、介護業界は違うんですよ。
提供するサービスの「公定価格」、つまり値段が、ぜーんぶ国によってガッチガチに決められちゃってるんです。
これが介護報酬の正体です。
「要介護3の人に、30分の身体介護をしたら〇〇円」みたいに、全部メニュー表みたいに決まってるわけ。
だから、施設がどれだけ素晴らしいサービスを提供しようと、ものすごいベテランの介護士さんが対応しようと、国から入ってくるお金は同じなんです。
ということはですよ?
施設の売り上げの上限が、最初から決まっちゃってるってことなんですよ。
これ、ヤバくないですか?
普通の会社なら、頑張って売り上げを2倍、3倍にすれば、社員の給料もドーンと上げられるかもしれない。
でも介護業界は、その「ドーン!」が構造的に無理なんです。
つまり、アナタの給料の源は、税金と介護保険料で賄われる「介護報酬」という、国が管理するお財布から出ているわけです。
国が「はい、今年の介護業界に使えるお金はこれだけね」って決めたパイを、全国の事業所で分け合っているイメージですね。
だから、景気が良くなったからって、急に給料が上がるわけじゃない。
むしろ、国の財政が厳しくなると、「ごめん、ちょっと介護報酬引き下げるわ」なんてことにもなりかねない。
恐ろしい話ですよね。
自分の頑張りとは全く別のところで、給料の天井が決められてしまっている。
これが、なぜ介護士は給料が低いのかという問いに対する、一番大きくて、そして一番厄介な答えなんです。
この大前提を、まずはしっかりと頭に叩き込んでおいてください!
専門性が正当に評価されにくい現状
さて、介護報酬のせいで給料の天井が低いって話はしましたけども。
それにしたって、「いやいや、それにしても安すぎないか?」って思いません?
だってアナタがやってる仕事、誰にでもできる簡単な仕事じゃないでしょうに。
ボクの息子が大変だった時、病院の看護師さんたちには本当にお世話になりましたけど、介護士さんの仕事も、それに負けず劣らず、ものすごい専門職だとボクは思うんですよ。
人の命を預かる、って言っても過言じゃないですよね。
認知症の方とのコミュニケーション一つとっても、ものすごい知識と経験、そして何より忍耐力が必要じゃないですか。
食事の介助、入浴の介助、排泄の介助…。
一つ間違えれば、誤嚥性肺炎だったり、転倒骨折だったり、命に関わる事故につながる危険と常に隣り合わせ。
それだけじゃない。
利用者さんの心のケア、ご家族との連携、日々の記録、レクリエーションの企画…。
もう、マルチタスクの極みですよ。
医療の知識も必要だし、心理学的なアプローチもいるし、体力ももちろんいる。
これだけのスキルを要求される仕事が、どうしてこんなに評価が低いのか。
ここにもね、根深い問題があるんですよ。
一つは、やっぱりさっきの介護報酬の話につながるんですけど、サービスの価格が「やったこと」で決まるだけで、「誰がやったか」の質の部分がほとんど評価されない仕組みになっていることです。
例えば、勤続10年の超ベテラン介護福祉士がやっても、昨日入ったばかりの未経験の人がやっても、同じ「身体介護30分」なら、施設に入ってくるお金は同じ。
これじゃあ、事業所側も「スキルが高いから」っていう理由だけで給料を大幅に上げるのが難しいわけです。
もう一つは、世間一般のイメージの問題もあるかもしれませんね。
「介護の仕事は、優しさがあれば誰にでもできる」みたいな、ちょっと誤解されたイメージが、まだどこかにあるのかもしれない。
そんなことないでしょう!
優しさだけじゃ、務まりませんよ、あんな大変な仕事。
アナタたちが日々磨いているその技術や知識、経験っていう「専門性」が、給料という形で正当に評価されていない。
これが、やりがい搾取なんて言葉が生まれる原因だし、多くの介護士さんが「報われない」と感じてしまう大きな理由なんじゃないでしょうか。
本当に、頭が下がる思いですよ。
でも、頭を下げられても、お腹は膨れないんです。
家族を養っていくことはできないんです。
この現実は、本当に厳しいと言わざるを得ませんね。
人手不足なのに給料が上がらないパラドックス
.png)
はい、次のテーマに参りましょう!
これがまた、不思議な話なんですよ。
アナタも職場で「人手が足りない!」って、毎日聞いてるんじゃないですか?
テレビや新聞でも「介護業界は深刻な人手不足です!」って、もう何年も前から言われ続けてますよね。
普通に考えたら、どうなります?
経済の基本中の基本、需要と供給のバランスってやつですよ。
働き手(供給)が少なくて、働き手が欲しい企業(需要)がたくさんあれば、当然、働き手の価値は上がって、給料も上がるはずじゃないですか。
「月給30万出すからウチに来てくれ!」
「いや、ウチは35万だ!」みたいな、人材の奪い合いが起きて、どんどん給料が上がっていく…。
これが、普通の市場原理ですよね。
でも、どうでしょう、介護業界は。
「人手が足りない、足りない」と叫ばれながら、なぜか給料は上がらない。
むしろ、安いまま。
これ、まさにパラドックス!
矛盾もいいところですよ。
じゃあ、なんでこんなおかしなことが起きるのか?
もう、アナタなら分かりますよね。
そうです、またアイツの登場ですよ。
「介護報酬」です!
結局、施設の収入源が国からの介護報酬でガッチリ固定されちゃってるもんだから、人手が欲しいからって、給料をポンと上げることができないんです。
上げたくても、上げるためのお金がない。
売上を増やすにも限界がある。
だから、他の業界みたいに「給料を上げて人を集める」っていう、当たり前の戦略が取れないんですよ。
その結果、どうなるか。
少ない人数で、現場を回すしかなくなる。
一人当たりの仕事の負担はどんどん増えて、残業も増える。
肉体的にも精神的にも、どんどんキツくなる。
でも、給料は上がらない。
…そりゃ、辞める人が増えるのも当然ですよね。
そして、人が辞めるから、さらに人手不足が深刻になる。
残った人たちの負担が、さらに増える…。
もう、完全な負のスパイラルじゃないですか。
「人手不足だから仕事がキツい」→「キツいのに給料が安いから人が辞める」→「さらに人手不足になる」という、地獄のサイクルが出来上がっちゃってるわけです。
この構造の中にいたら、そりゃ心が折れますよ。
将来に希望なんて持てなくなります。
「なぜ介護士は給料が低い」という問題の根っこには、この「人手不足なのに給料を上げられない」という、業界特有の致命的なバグが存在してるんです。
これは個人の努力だけでは、どうにもならない壁と言えるかもしれませんね。
非正規職員の多さが平均給与を下げる一因
さあ、どんどん行きましょう。
次に注目したいのが、「働き方」の問題です。
アナタの職場にも、パートさんとか、派遣さんとか、いわゆる非正規で働いている方、たくさんいませんか?
実は、介護業界って、他の業界に比べて、この非正規職員の割合が結構高いんですよ。
もちろん、いろんな事情があって、あえてパートを選んでいる方もたくさんいると思います。
「子育てと両立したいから」とか、「自分のペースで働きたいから」とかね。
それはそれで、素晴らしい働き方の一つです。
でも、これが業界全体の給料を考える上では、ちょっと厄介な問題を引き起こしている側面もあるんです。
どういうことかと言うと、当然ですけど、一般的に非正規職員の方の給料って、正職員に比べると低く設定されていますよね。
時給制だったり、ボーナスがなかったり。
で、業界全体で働く人のうち、この非正規職員の割合が高いと、どうなるか。
そうです。
業界全体の「平均給与」が、ガクッと下がっちゃうんですよ。
例えば、5人の職員がいて、
正職員3人(月給25万円)
非正規職員2人(月給15万円)
だとすると、平均は21万円になりますよね。
これがもし、全員正職員だったら、平均は25万円なわけです。
この数字のマジックが、結構大きい。
世間から「介護士の給料は安い」って言われる時、この平均値で見られちゃうことが多いんです。
じゃあ、なんで施設側は非正規職員をたくさん雇うのか?
もちろん、働く側のニーズがあるというのも一つですけど、経営的な視点で見ると、やっぱり人件費を抑えたい、という正直な理由があります。
またまた介護報酬の話に戻りますけど、収入が限られている中で利益を出すには、一番大きなコストである人件費をどうにかコントロールするしかない。
正職員をたくさん雇うよりも、非正規職員を組み合わせた方が、経営的には柔軟に対応できる、というわけです。
シフトの穴を埋めやすかったりもしますしね。
でも、これが働く側にとっては、なかなか厳しい状況を生みます。
非正規職員が多いことで、業界全体の給与水準が低く見られがちになり、それが「介護の仕事=安い」というイメージを定着させてしまう。
そして、その安いイメージが、新しく業界に入ってくる人を遠ざけ、人手不足を加速させる…。
これもまた、負のスパイラルの一因と言えるでしょう。
正職員で働いているアナタにとっても、決して他人事じゃないんです。
業界全体のイメージが低ければ、アナタ自身の給料も、なかなか上がっていかないですからね。
仕事内容と給与のバランスが取れていない
.png)
はい、この章の最後になりますけども。
ここまで、制度とか、仕組みとか、ちょっと小難しい話をしてきました。
でも結局、一番言いたいのは、ここかもしれません。
単純に、
「仕事、めっちゃ大変すぎませんかっ!?」
「その大変さに、給料が見合ってなさすぎませんかっ!?」
っていう、魂の叫びですよ!
ボクはサラリーマン時代、デスクワークが中心でしたけど、それでも「あー、疲れた」なんて言ってました。
でも、介護の仕事は、そんなレベルじゃないでしょう。
まず、肉体的な負担がすごい。
人を抱えたり、支えたり、一日中立ちっぱなし、動きっぱなし。
腰とか膝とか、絶対悲鳴をあげてますよね。
夜勤もあるわけじゃないですか。
生活リズムはガタガタになって、体調を維持するだけでも大変。
ボクの妻も、息子が小さい頃は夜泣きで寝不足になって、本当につらそうでしたけど、それを仕事でやるって、想像を絶しますよ。
そして、それ以上にキツいのが、精神的な負担じゃないでしょうか。
人の「生と死」に、これほど向き合う仕事って、なかなかないですよ。
昨日まで笑顔で話していた利用者さんが、今日、静かに旅立たれる。
そんな経験を何度も繰り返して、そのたびに心を揺さぶられ、でも、次の瞬間にはまた笑顔で他の利用者さんと接しなければならない。
認知症の方から、心ない言葉を投げつけられることもあるでしょう。
理不尽な要求に、ぐっとこらえなきゃいけない場面もあるでしょう。
ご家族からのプレッシャーもあるかもしれない。
感情のコントロールが、ものすごく難しい仕事だと思うんです。
自分の心をすり減らしながら、誰かのために尽くす。
本当に尊い仕事ですよ。
でも、その対価が、他の仕事より低いって、どういうことなんですかね?
この「仕事の大変さ」と「給料の安さ」の、ありえないくらいのアンバランス。
これが、なぜ介護士は給料が低いという問題の、一番本質的な部分であり、働く人たちの心を最も深くえぐる部分なんだと、ボクは思います。
「やりがい」という言葉は美しいです。
でも、「やりがい」だけでは、生活はできない。
家族を守ることはできないんですよ。
この現実に、アナタはずっとフタをして、見ないふりをしていませんか?
でも、もう、その必要はありません。
次の章から、いよいよこの泥沼から抜け出すための話をしていきますからね!
========================
【PR】 タケパトのおすすめアフィリエイト教材
Tipsビジネスランキング1位!
資金なし、スキルなし、知識なしでもできる!初心者向け
X(ツイッター)とスマホだけで簡単副業!
爆速収益化!3ヶ月で月30万円 1年で月100万円目指せる
詳しい教材のレビューはこちら
なまいきくん流X運用術【The.X】)))))))))))))).jpg)
================
なぜ介護士は給料が低い状況から脱却すべきなのか
この章のポイント
- 将来性を見据えたキャリアアップの重要性
- 処遇改善加算を賢く活用する事業所選び
- 介護保険制度に依存しない収入源の確保
- 介護福祉士などの資格取得で給料を上げる方法
- まとめ:なぜ介護士は給料が低い問題は個人で解決できる
将来性を見据えたキャリアアップの重要性
.png)
さあ、お待たせしました!
ここからが本番ですよ!
前半では、アナタがいかに大変で、いかに報われない構造の中にいるかっていう、ちょっと気が滅入る話をしちゃいました。
でも、それはあくまで現状分析ですから。
大事なのは「じゃあ、どうすんのよ!?」ってことですよね。
まず、多くの人が考えるであろう道、それが介護業界の中での「キャリアアップ」です。
今のままじゃラチが明かないから、リーダーになったり、ケアマネージャーになったり、施設長を目指したりして、給料を上げていこうぜ!
っていう、まあ、王道のルートですね。
もちろん、これは一つの正解です。
実際に、役職がつけば役職手当がもらえますし、資格を取れば資格手当がつくところも多いでしょう。
今の年収が300万円だとしたら、ケアマネになって400万円、施設長になれば500万円、600万円…なんていう未来も、決して夢物語ではないかもしれません。
これは、自分の将来性を考えて行動する、という意味で、非常に重要な視点だと思います。
ただね、ここでボクは、あえて、ちょっと意地悪な質問をしたい。
「アナタ、そのキャリアアップの先に、本当に望む未来はありますか?」
って。
考えてみてくださいよ。
役職が上がるってことは、責任もめちゃくちゃ重くなるってことですよね。
現場の仕事に加えて、部下の管理、シフトの作成、ややこしいクレーム対応、山のような書類仕事…。
現場が好きでこの仕事を選んだのに、気づけばパソコンの前で頭を抱える時間ばかりが増えていく。
給料は上がったかもしれないけど、その分、自分の時間と精神は、さらに削られていく。
…それって、本当にアナタが望んだ姿ですか?
ボクは、息子が倒れたあの日、心の底から思ったんです。
「お金も大事。
でも、時間も同じくらい、いや、それ以上に大事だ」って。
家族との時間、自分のための時間。
これを犠牲にしてまで、会社組織の歯車として上を目指すことに、何の意味があるんだろうって。
だから、キャリアアップを考えるのは素晴らしいことだけど、それが「会社に、より深く縛られる道」だとしたら、一度立ち止まって考えてみてほしいんです。
その先に待っているのは、少しだけマシな給料と、今よりもっと不自由な毎日、なんてことになっていませんか?
ボクがこれから話すのは、この「会社に縛られる」という大前提そのものを、ぶっ壊すための話です。
将来性を考えるなら、業界の中の未来だけじゃなく、業界の外にも目を向けてみる。
その勇気が、アナタの人生を劇的に変えるんですよ。
処遇改善加算を賢く活用する事業所選び
さて、キャリアアップと並んで、よく給料アップの方法として語られるのが、この「処遇改善加算」ってもんですよね。
なんだか、また難しい言葉が出てきましたけども。
これは、国が「介護士さんの給料、あまりに安すぎてヤバいから、ちょっとテコ入れしますわ!」ってことで始めた制度です。
ざっくり言うと、ちゃんと職員のキャリアアップの仕組みを整えたり、働きやすい環境を作ったりしてる事業所に対して、国が介護報酬を上乗せで払ってくれるんですね。
で、その上乗せされた分は、「ちゃんと職員の給料アップに使ってね!」っていう、まあ、ありがたい制度なわけです。
これのおかげで、数万円単位で給料が上がったよ、っていう人も実際にいると思います。
だから、もしアナタが転職を考えているなら、この処遇改善加算をちゃんと取っていて、それをしっかりと職員に還元しているクリーンな事業所を選ぶ、っていうのは、ものすごく大事なポイントになります。
求人票とかに「処遇改善加算Ⅰ取得」とか書いてあるところは、比較的ちゃんとしてる可能性が高い、ってことですね。
これは、もう、転職の際の必須チェック項目と言ってもいいでしょう。
でもね。
でも、ですよ。
ボクは、これも結局のところ、「対症療法」でしかないと思うんです。
風邪ひいて熱が出たから、解熱剤を飲む、みたいな。
一時的に熱は下がるかもしれないけど、風邪のウイルスが体から消えたわけじゃない。
処遇改善加算も同じで、国が「加算しまーす」って言ってるうちはいいですよ。
でも、もし国の財政がもっともっと厳しくなって、「やっぱ、加算やめまーす」ってなったら、どうします?
一夜にして、アナタの給料が数万円、ポーンと消し飛ぶ可能性があるんですよ。
怖くないですか?
自分の給料が、国のさじ加減一つで、いとも簡単に上がったり下がったりする。
これって、自分の人生の決定権を、国に預けちゃってるのと同じじゃないですか。
ボクは、それがたまらなく嫌だった。
息子が苦しんでいる時に、「国が…」「会社が…」なんて言ってる場合じゃなかった。
自分の力で、誰にも文句を言わせないくらい、稼ぐ必要があったんです。
処遇改善加算は、もらえるなら、ありがたくもらっておく。でも、それに決して依存してはいけない。
それは、アナタの命綱じゃないんです。
言ってみれば、国からもらった、ちょっとしたオマKEみたいなもの。
本当の命綱は、自分自身で作り出すしかないんですよ。
その具体的な作り方を、いよいよ次のテーマでお話しします!
介護保険制度に依存しない収入源の確保
.png)
お待たせしました!
ここからが、この記事の核心部分!
ボクが、アナタに一番伝えたいことです!
ここまで散々、介護報酬だの、処遇改善加算だのって話をしてきました。
もう、お分かりですよね。
なぜ介護士は給料が低いのか、その根本原因は、アナタの収入が「介護保険制度」という、国が作った巨大なシステムに、100%依存しちゃってるからなんです。
このシステムの中にいる限り、アナタは、国が決めたルールの範囲内でしか、お金を稼ぐことができない。
国が決めた天井の下で、もがき続けるしかないんです。
じゃあ、どうすればいいか。
答えは、シンプル。
「そのシステムの外に、自分の力で、もう一つお財布を作ればいい」
んですよ!
つまり、介護の仕事とは全く別のところで、収入源を確保するってことです。
これこそが、ボクがどん底の生活から這い上がることができた、唯一の方法でした。
「副業」ってやつですね。
「いやいやタケパトさん、そんなこと言ったって、介護の仕事はただでさえキツくて、そんな時間も体力も残ってませんよ!」
って声が聞こえてきそうですね。
分かりますよ、もちろん。
だから、夜勤明けにコンビニでバイトするとか、休みの日に工事現場で働くとか、そういう体力勝負の副業を勧めるつもりは、毛頭ありません。
そんなことしたら、体を壊して、本業まで続けられなくなっちゃいますから。
ボクが提案するのは、
スキル無し、経験なし、知識なし、資金なしでも始められて、
いつでも、どこでも、アナタの好きな時間にできて、
スマホ一台あれば、自宅のベッドの上でも、通勤電車の中でも、休憩中のロッカールームでも作業できちゃう、
そんな、魔法のような副業です。
それが、「アフィリエイト」なんです。
アフィリエイトって、聞いたことありますか?
簡単に言うと、「ブログとかSNSで、企業の商品やサービスを紹介して、それが売れたら紹介料がもらえる」っていう仕組みです。
ボクは、このアフィリエイトを、X(旧Twitter)とスマホだけでやってます。
これの何が凄いって、一度仕組みを作ってしまえば、アナタが寝ている間も、介護の仕事をしている間も、息子さんと遊んでいる間も、24時間365日、勝手にお金を稼ぎ続けてくれる可能性があるってことなんです。
これって、時間を切り売りしてお金をもらう、アナタの今の働き方とは、全く次元が違うと思いませんか?
介護の仕事で、安定したお給料をもらいつつ、
スマホ副業で、青天井の収入を目指す。
この「収入の柱が二つある」という状態が、どれだけアナタの心に余裕と安定をもたらすか、想像できますか?
もう、理不尽な上司に頭を下げ続ける必要もありません。
「給料が安い…」って、ため息をつく毎日ともオサラバです。
「この仕事、辞めたかったら、いつでも辞めてやる!」
そんな、圧倒的な精神的自由が手に入るんですよ。
これこそが、介護保険制度という巨大な檻から脱出するための、唯一にして最強の鍵なんです!
介護福祉士などの資格取得で給料を上げる方法
と、まあ、副業の魅力について熱く語ってしまいましたけども。
もちろん、本業である介護の仕事で、給料を上げていく努力を否定するわけじゃありませんよ。
両方やれば、最強じゃないですか。
で、介護業界で給料を上げる、一番分かりやすい方法が、「資格を取る」ことですよね。
特に、「介護福祉士」という国家資格。
これは、持っていると資格手当が月5,000円~10,000円くらいつく事業所が多いですし、何より、アナタの専門性を証明する大きな武器になります。
転職する時にも、圧倒的に有利になりますからね。
実務経験を積んで、試験に合格する必要があるので、簡単ではありませんが、これは介護のプロとして働き続けるなら、絶対に目指すべき資格だと思います。
他にも、ケアマネージャー(介護支援専門員)になれば、さらに給料は上がりますし、仕事の幅も広がります。
ただ、これは現場を離れてデスクワーク中心になるので、向き不向きがあるかもしれませんね。
他にも、喀痰吸引等研修とか、認知症ケア専門士とか、持っていると「おっ」と思われる専門的な資格はたくさんあります。
こういう資格を取って、自分の市場価値を上げていく。
これは、会社に給料を上げてもらうための、正当な「交渉材料」を手に入れるということです。
素晴らしいことですよ。
でもね、ボクはやっぱり思っちゃうんです。
めちゃくちゃ頑張って勉強して、難しい国家試験に受かって、それで月給が1万円上がりました!
…果たして、その努力とリターンは、見合ってますか?
もちろん、お金だけが目的じゃないのは分かります。
知識が増えれば、より良いケアができるようになるし、仕事のやりがいも増すでしょう。
それは、本当に尊いことです。
でも、もしアナタが、純粋に「もっとお金が欲しい!」「生活を楽にしたい!」って思ってるなら、その努力の矛先を、少しだけ別の方向に向けてみてはどうですか?
って、ボクは言いたい。
資格の勉強に使う時間の一部を、スマホ副業の勉強に使ってみる。
そうすれば、月1万円どころか、月5万、10万、あるいはボクみたいに100万円っていう、資格手当とはケタの違う収入を得られる可能性があるんですよ。
資格取得は、いわば「守り」のスキルアップ。
今の会社、今の業界で、少しでも良い待遇を得るためのものです。
でも、ボクが教えているスマホ副業は、「攻め」のスキルアップ。
今の環境がどうあろうと、自分の力で未来を切り拓いていくための、全く新しい武器なんです。
どっちがワクワクしますか?
ボクは、断然、後者でしたね。
まとめ:なぜ介護士は給料が低い問題は個人で解決できる
.png)
さあ、長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございます!
いよいよ、まとめに入りますよ。
なぜ介護士は給料が低いのか。
その答えは、介護報酬を筆頭とする「国の制度」という、個人ではどうにも動かせない、巨大な壁があるからでした。
アナタの頑張りが正当に評価されにくい、悲しい構造があるからでした。
この構造の中で、文句を言ったり、国の政策が変わるのをただ待っていたりしても、残念ながら、アナタの生活は1ミリも良くなりません。
会社にキャリアアップを期待しても、処遇改善加算を当てにしても、それは結局、誰かにコントロールされた人生から抜け出すことはできないんです。
でも、もう嘆くのはやめにしましょう。
答えは、もう出ているんですから。
「なぜ介護士は給料が低い」という問題は、
国が解決してくれるのを待つんじゃない。
会社が解決してくれるのを待つんじゃない。
アナタ自身の力で、今すぐ、解決できる問題なんです!
そのための最強の武器が、ボクが人生を賭けて実践してきた、スマホとSNSを使ったアフィリエイトという働き方です。
介護の仕事は、本当に尊い仕事です。
アナタを必要としている人が、たくさんいます。
だから、もしアナタがその仕事に誇りを持っているなら、続けてほしい。
でも、「お金のために」我慢して続ける必要は、もうどこにもないんです。
介護の仕事は、「やりがい」と「社会貢献」のためにやる。
そして、お金は、スマホ副業で、好きなだけ稼ぐ。
そんな、最高の生き方ができる時代なんですよ、今は!
ボクは、息子が病気になったあの日、絶望の淵にいました。
でも、あの絶望があったからこそ、今の自由な生活を手に入れることができた。
人生、何がきっかけになるか、分かりませんよ。
アナタが今、「なぜ介護士は給料が低い」って感じているその怒りや不安は、アナタの人生を変えるための、最高のガソリンになるんです。
スキルも、経験も、資金も、何もいりません。
必要なのは、アナタが今持っているそのスマホと、「現状を絶対に、変えてやる!」っていう、ほんの少しの勇気だけ。
ボクが紹介する有料教材には、ボクがゼロから月100万円稼げるようになった、全ての知識とノウハウが、これでもかってくらい詰め込まれています。
アナタは、ただ、その通りに真似して、コツコツ続けていくだけ。
もちろん、楽して稼げるなんて、そんなうまい話はありません。
最初の数ヶ月は、ほとんど収益にならないかもしれない。
でも、そこで諦めずに続けていれば、必ず、未来は開けます。
ボクが、その証人ですから。
さあ、どうしますか?
これからも、給料明細を見てため息をつきながら、国の制度に文句を言い続ける人生を送りますか?
それとも、今日この瞬間を、自分の力で人生のハンドルを握り直す、記念すべき第一歩にしますか?
選ぶのは、アナタです。
ボクは、アナタの勇気を、全力で応援しますよ!
この記事のまとめ
- 介護士の給料は国の介護報酬制度で上限が決まっている
- 素晴らしい専門性や仕事内容が給与に反映されにくい
- 人手不足なのに給料が上がらないという構造的矛盾がある
- これらの問題を国や会社のせいにしても人生は変わらない
- 現状を打破する鍵は制度の外に収入源を作ること
- スマホとSNSを使ったアフィリエイトが最適な解決策
- スキルや経験や資金がなくても誰でも始められる
- 時間や場所に縛られず自分のペースで実践可能
- 介護の仕事と両立しながら収入の第二の柱を築ける
- 将来的には本業を超える収入を得て経済的自立を目指せる
- 収入が増えれば精神的な余裕が生まれ本業にも好影響が出る
- 「給料が低い」という悩みから解放される自由が手に入る
- 必要なのはスマホと「変わりたい」という強い意志だけ
- 僕が実践した具体的な方法はすべて有料教材で学べる
- アナタの人生を変えるチャンスは今ここにある
========================
【PR】 タケパトのおすすめアフィリエイト教材
Tipsビジネスランキング1位!
資金なし、スキルなし、知識なしでもできる!初心者向け
X(ツイッター)とスマホだけで簡単副業!
爆速収益化!3ヶ月で月30万円 1年で月100万円目指せる
詳しい教材のレビューはこちら
なまいきくん流X運用術【The.X】)))))))))))))).jpg)
================